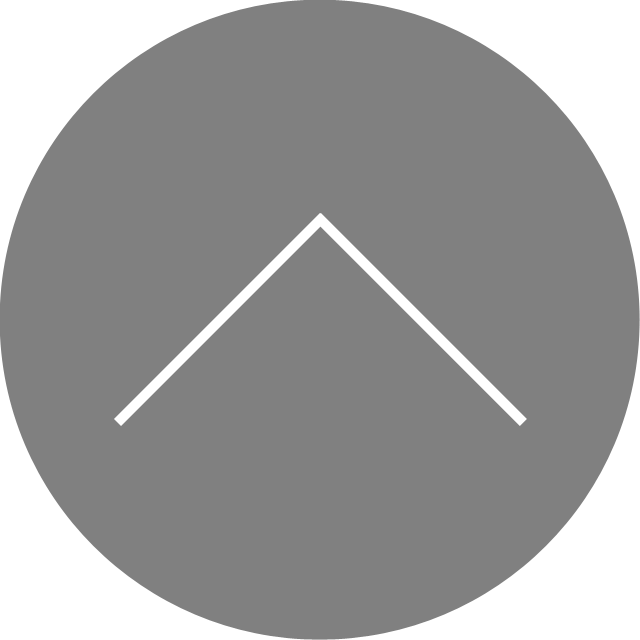主張
2018年05月08日
平成21年12月10日(雑記より)
児童手当と子ども手当議論における一考察
そもそも、児童手当の目的は、「児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資すること」だという。果たしてその目的に応じた支出がされているのかは各家庭の事であり判らないが、児童扶養手当等の福祉的措置という大義名分も薄い施策である。
経済低迷による失業等に応じた子育て支援策としてならそれも必要であろう。何が何でも一律という策が問題なのだ。おまけに今は衣料品はフリーマーケット等には子供服が溢れ、価格も安い。食事も贅沢を言わなければデフレ価格である。幼児期や義務教育課程における子供への支出はたかが知れている。金に困るのは中学期から高校期である。
今、深刻な問題は少子高齢化対策である。この先、少子化が続くと就業人口の減少が更に加速され、高齢者福祉施策が今のままだと、とても現在の福祉施策も追いつかない状況となるであろう。子ども手当に関しては少子化対策の一環ではないのであるが、少子化対策としてこんな案はいかがだろうか。
女性の晩婚化、出生率の低下はまさに国の危機である。晩婚化は即ち初産年齢が高くなり、第二子、第三子を産むことも少なくなるのは当たり前である。故に出生率の低下をもたらす。しかしながら、一昔を考えてみると、我々の親の年代、すなわち昭和初期から敗戦後前後の兄弟姉妹は七人とか10人とかの兄弟を持った世帯がザラにあった。現代の人から見ればあの貧しい時代にさえだ。晩婚云々は別にして、かなりの年齢となっても子供を産んできたようだ。子供を産み育てると言うのが経済性と関係があるか無いか。私の結論は無くは無いと思うし、あるに越したことはない。
昔と違う終身雇用制が無くなったことはかなりの痛手である。給料だけでなく、旦那の雇用自体への心配が妻となる、母親となる女性の心配事の一つでもあろう。
議会でも度々取り上げられるのが、待機保育園児問題である。今はこれでもかと言うくらいに保育園に通わせたい親が多い。少子化と言われる中、公立幼稚園は定員割れが生じていても、保育園は大人気である。それだけ、両親共働き世帯が多いという事だが、果たしてこの状況を「良し」とはしたくない。
特に乳幼児保育については、何で親が赤ちゃんを他人に預けられるのかが不思議なことである。いや、家庭それぞれの事情があるからそれは言うまい。ただ、保育料を払ってまで奥さんが得る収入は生活する上で無ければならないお金なのかと言わずにはいられないのである(もちろん、母子家庭や事情があって働かなくてはならない家庭はある)。
私は赤ちゃんの味方である。おなかが空いた時やおむつを取り替えてもらいたい時には泣く。「お母さん来て」と呼んで泣く。おっぱいも出来れば母乳が欲しい。安心する。お昼寝の時もお母さんのぬくもりの中で寝たい。僕は、少しばかりお金が無くったって、お母さんと一緒に居たい。これが赤ちゃんの気持ちだと信じている。
3歳児神話を崩そうと企んでいる大人が居ることも知っている。でも、他の動物と違って、人間の子はゆっくりと成長していく。その時には親が必要なんだ。昔の人は赤ちゃんをおんぶしても仕事してきた人もいる。赤ちゃんの傍には必ずお母さんが居なければならない。子供の為にも。
経済力が子育てに無関係だとは言っていない。でも昔も今も、子供の成長過程にお母さんが居るか居ないかは子供にとって大きな問題である。子供がせめて3つか4つになるまでは、お母さんは子育てに熱中してほしい。
だからこそ、もし児童手当や子ども手当を考えるなら、出生から4歳頃までの子供がいる世帯には、保育料程度の家庭保育手当なりを支給して、家庭で子育てする環境を作ってあげて、自分の手で子育てをする喜びを与え、兄弟が居れば尚楽しいと思えば、弟や妹を産んでやれるのではないか。
「これからは社会が子育てをする時代」では無く、「子育ては家庭で行うもの」にしていかなくてはならないと思う。親がいつもそばに居る赤ちゃん期をおくった子供は、同じように赤ちゃんを放さないと思う。
少子化対策には程遠いかもしれないが、やはり家庭における子供の位置づけが大事であろう。子供は生活の邪魔者ではないし、いつでも子供の傍に居れば、生活の中で充実した毎日が送れる。
「家庭での子育て応援」を目的とした手当支給なら、大歓迎であるが、目的も訳わからない施策はお断りである。
『追悼・平和折念のための記念碑等の在り方を考える懇談会』の最終報告書に対する一考察
(平成14年12月24日日記参照)
同僚議員の一般質問における私の考え(平成14年12月16日 日記参照)
「夫婦別姓」と称する民法改正法案が5年ほど前、論議されたことがある。そしてまた突如復活し、法案が提出されようとしているらしい。小田原市女性行政課が発行するJメール(JYOJYOからJメールになった)によると、小田原市職員意識調査における夫婦別姓についての質問で、男女とも「同姓・別姓は本人に選択させるべき」という回答が多く、男は39.9%。女は59.9%にものぼっている。また、特集のなかで、ある夫婦が「夫婦同姓を強制するのは人格権侵害」と憲法13条違反で家裁に不服申し立てを行なった事例を紹介している。そもそも人格権とは何なのだ。あるテレビでフェミニストを自称する者がやはり「人格」が傷つけられることで夫婦別姓を賛美していたことがあった。
自分はこう考える。夫婦となる者、いやそれ以外でも完璧な人格者はいない。だからこそ、お互いを尊重しつつ、自分のそして相手の足りないところを補いながら夫婦生活を送り、ささやかながらも最小単位の集合体である家庭を持ち、子孫を残し人生を全うする。それが普通の夫婦の姿だと思う。
そこには、人格権がどうだこうだとの議論を持ち込む余地等ないと思う。もし、人格権が侵されるのなら、その人間と夫婦となった事を呪い、恨み、反省し、悔やめばよいだけである。これは個人の問題なのだ。
もし、職業や通常の生活の中で別姓でないと都合が悪いのであれば、通称として使用すればよいだけである。現状でもそれは規制されていないのではないか。
戸籍をいじって得るものとは何だか理解できない。男に搾取されているとでも言いたげに「現行の民法では、男女どちらの姓を選択しても良いのですが、現実には、97.2%が夫側の姓を名乗っています。」(Jメール文中)と書かれている。それはそれぞれの夫婦が決めたことであり、明治民法下の「家」制度と現在も変わっていないような記述となっている。
今、社会問題となっているの青少年の非行、犯罪は、家庭すなわち親に起因していると言われる向きが強いことは誰だって指摘する。まさに「家」の崩壊がもたらした現状でもあると思う。
家族は形ではない。しかし、形すら無くなったらどうなるだろう。父と母が別の姓で、子どもはどうなるのか。2人の子どもが別々の姓を持つ事もあるのが自然なのか。
あたかも5年前の論議に終止符を打った安室奈美恵の言葉を思い出す。
「明日から丸山奈美恵になります。」
多くの女性が男性の姓だろうが女性の姓だろうが、同じ姓を名乗ることに喜びを感じているのではなかろうか。無理に民法を改正しなければならない程の追い詰められた現状とは思えないのである。(平成13年10月14日の日記より)
小泉総理の靖国神社参拝について
小泉総理が昨日靖国神社に参拝された。総裁選挙、参議院選挙と一貫して8月15日の参拝を公言していただけに誠に残念でならない。公約違反でもある。しかしながら、小泉総理の苦渋に満ちた表情を伺うと、これは俗に言う抵抗勢力はいままで言われていた方々よりも福田官房長官をはじめ、田中外相、YKKなど総理側近が一番の抵抗勢力であった事が原因だと思う。結局本日のマスコミ各社の番組では、やっぱり足して2で割った様な行動は、双方から批難されている。靖国神社を殊更軍事国家の象徴とする輩は本当に神社を訪れ、宝物館をはじめとする施設を見学したことがあるのだろうか。だれも粛々と頭を垂れ英霊が安らかに眠らんとする事を願い、英霊の礎の下に現在の平和な世の中がある事を誰もが感謝する。これが普通の姿ではないのか。宗教を超え、国家がその国の繁栄を信じ犠牲となった者を国民総意で敬いおまつりすることはとても自然な事であり当然のことである。そこで国立墓地のような構想があるが、これは「靖国で会おう」と散華された英霊に対して誠に失礼な現代の価値観での考えである。靖国神社国家護持が私の信条である。宗教法人という垣根をどう超えるか課題はあるにしても靖国神社は平和の象徴であると常に思っている。国家に殉じた者を国家が(どういう形態であれ)お参りしなければならない。個人の宗教の相違があるのであれば個人の墓で独自の宗教でお参りすれば良い。その事は既に最高裁での判例を示すまでもなく、国家が宗教行事を通じその効果が期待されるもの以外は憲法20条に違反しないことが示されている。ただこの20条も所詮GHQによる日本の歴史、慣習をたたき潰す目的で作成したものだから憲法第1条は認めようとせず、20条は金科玉条のごとく振りかざす輩が言っているだけに過ぎない。
今回の前倒し参拝は中国、韓国からの外圧を受けて日本側が折れた見方を諸外国からされるであろう。これが国益にどのような結果をもたらすか心配である。勿論「聖域なき構造改革」も然りである。今回の行動、言動を見ていると一番無念の気持ちを持っているのは小泉総理自身でもあるだろう。怒りや嘆息を通り越し、小泉総理にはお気の毒と言ってあげるしかない。
(H13.8.14記)
朝から小泉首相の靖国神社公式参拝特集でいくつかの番組をはしごしてしまった。まず、中国や韓国が反発しているからやめるべきだという意見はおかしい。このことは内政干渉であり、与党野党共に反発すべきなのに、その要求を自分の主張に置き換えている者が目につく。また憲法問題では正月の首相による伊勢神宮参拝には口を閉ざしながら靖国神社参拝にはヒステリックに反発する勢力、村山元首相も参拝していると思うが・・・。いろいろと議論はあるが、結局のところ、自民党総裁選挙、参議院選挙を通じて「8月15日には靖国神社に参拝する」と公言していたのが小泉総理であり、ご承知の通り自民党の圧倒的勝利に終わっている。特に野党は小泉総理の「聖域なき構造改革」をはじめ、靖国発言をも批判の対象として参議院選挙を戦っていたではないか。そして敗北したではないか。靖国問題は総理、そして外務大臣が公式参拝することでケリがつく。靖国に参拝する事でまた軍事国家になる恐れが・・・等との妄言やある議員のように天皇への忠誠を尽くした(個人的にはそうでなくてもそれは個人の心の問題)者へ首相が参拝するのはおかしいなどと個人的思想を押しつける様な言動は議論に値しない。正々堂々と小泉総理は靖国神社に参拝に行くべきである。
私は毎年、先の大戦で亡くなった多くの英霊の方々への感謝と畏敬を、国旗を半旗にすることで表している。(H13.8.12記)
子供が少年院送りになった保護者は、保護者として認められないことなんだ。
(8月8日の日記から)福祉文教常任委員会を傍聴する。11件の所管報告事項の中で、委員も注目したのは7月に起きた中学生による暴行事件2件であった。学校名、個人名は伏せてあり、既に逮捕されて少年鑑別所から観察処分になっているものや現在鑑別所に入れられているとの報告だが、いずれも数十日の間には普段と変わらぬ生活(と言ってもどうせ荒んだ生活だと思うが)をぬくぬくと送るに違いない。委員からは加害者は今後どのような事になるのかとの質問があったが、被害者(一人は教員、一人は加害者の下級生)へのケアについての質問は聞けなかった。そもそもこれらの事件は加害少年がいなければ起きえない事件である。鑑別所を出て保護観察か少年院かわからぬが、いつかは戻ってくる。被害者からすればこの事件は、加害者が更生をし、謝罪をした時点でようやく安堵するだろう。それまではおちおち眠れない事は目に見えている。しかしながら、短期間で更生など出来る訳がない。それはすでに十数年間という長い間に培われた性格、生活環境によってもたらされた結果であるからである。事件を起こし、逮捕され、鑑別所に送られ家裁によって観察か、少年院かの判断をされてシャバに出てくる。この間、特に少年院に送られ更生の可能性がある少年も結局再犯を重ねる事も多いと聞く(少年院側は再犯少ないという)が、本当のところはわからない。これより持論を展開する。そもそも少年院は入院した少年を従来の保護者に代わり保護する役目を持つ。と言う事は言い換えれば欠格がある保護者にその原因があると言ってもよいことになる。それでは、少年院から出た者がなぜ再犯を重ねるのか。それは少年犯罪の原因といわれた親(保護者)側がその責任、欠格に対する処方が何も行われずに旧態依然のままの状態で再び退院少年を受け入れてしまうからだと考える。以前、松山や奈良の少年院にも視察をしたことがある。退院間近の院生は家族とともに少年院内の特定の部屋で数日過ごしてから退院する事もある様だ。それ自体は素晴らしい事だ。親子とのふれあいやすれ違いとなってしまった環境を取り戻すために大いに行ってもらいたい。しかし、先にも述べた通り、保護者自身が本当に退院生を受け入れるだけの器量、すなわち保護者としての自覚を持っているかは疑問だ。それは、だれも保護者に対して指導、助言、教育を施す事が無いからである。少年院生の退院期間は保護者の受け入れ環境、教育成果等を考察し、受け入れ可能となった時点で退院させることではいかがであろうか。いつまでも現行法制度が絶対的なものである訳がない。様々な創意を施し、法の執行の裏側でなすべき事を実践しなければ何度も同じ事を繰り返すのみである。
このままでいいの?!平和ボケの日本に憂慮!
6月8日の大阪教育大学附属池田小学校で起きた児童殺傷事件は、余りにも痛ましい惨劇であった。罪もないまま短い生涯を閉じた8名の児童の冥福を心から祈ると共に、未だ傷を負い治療に専念する負傷された先生や児童の一日も早い回復を併せてお祈りします。また、事件に遭遇した児童の心の傷は恐らく癒えることなく生涯にわたって続くものとみられ、キチガイ(差別用語かわからないが、反社会的行動を取り、尋常の神経を持たぬ俗に言う触法精神障害者という言葉は売春を援助交際と言うが如き現象と同じであり、キチガイはキチガイである)である犯人の宅間守により苦痛を与えられた幼い児童が今後どのような人生をおくるのか、十分なケアが施されるように思うのは全国民の願いであると思う。
この事件以降、全国で何件も模倣犯や、不審人物の出現に怯える学校は、校門の施錠、独自で安全管理対策やパトロールの強化、催涙ガスの教室への設置等の対策を講じ、児童が安心して通える学校運営に血眼になって取り組んでいる。我が母校も早速に同様対策を講じており、保護者の不安もピークにある今日、いわゆる触法精神障害者が完全に野放し状態の社会を改善していかない以上、同じ事件が繰り返される事は必至である。
ある評論家や政治家には、犯人をつくり出した社会が悪いと切って捨てる発言もあるようだが、その社会を作っている一員に自分も含まれている事を忘れているのか、傍観者的発言には憤りを覚える。税金を滞納しようが、痴漢をやろうが、万引きをしようが、国会議事堂で立ちションをしようが、殺人をしようが、何でもかんでも社会が悪いと決めつけるような輩の発言をメディアで公然と垂れ流されるような状況は、もうこの辺で終わりにしよう。今や法治国家ならず放置国家といわれる所以である。
このことは、今回の事件だけではなく、日常でも当たり前のように無法地帯と化した状況はゴマンとある。
盗難車での集団暴走行為、不起訴処分で強制送還されるだけの外国人犯罪、執行猶予付き判決でも繰り返される薬物犯罪等、多くの国民が日毎危険にさらされ、不安な毎日を送らねばならない今の日本は、果たして安全神話なる過去の冠は既に取り払われているに違いない。
治安を守る立場の警察も、急速な犯罪発生件数に追いつかないほど人的には不足していることは誰の目に見ても明らかである。特に情報通信技術の進歩による犯罪や不法外国人、犯罪の低年齢化の増加への対応とともに従来からの事故処理、車庫証明、放置自転車や不審車の照会等に限らず、不法投棄、ささいな喧嘩、近所のステレオの音がうるさい等の苦情も警察を頼る国民は後を絶たず、まさに「何でも屋」になってしまっている。警察の仕事を分割し、車庫証明(一部警察OBが受け持っているようだが数は少ない)や放置自転車登録確認及び処理作業等は警察OBの方々に協力を依頼し、委託すべきであると思う。
そこで、人々が平和で安全に安心して生活出来るためには、何が必要か。お金が欲しい。家を建てたい。車が欲しい。老後が心配。女性の地位向上。男女平等参画化社会。減税。小児医療無料化。景気回復。人々が求めるものは沢山ある。しかしながら、自らの命無くしては意味もない事である。国防においても同じである。国家なくしてはそんな理想は絵に描いた餅となる。今や平和な日本を取り戻すには、法治国家らしく社会安寧政策を真っ先に施さねばならないと思う。警察官の増員、法整備は国会が動かねばなるまい。(オウムによるテロ活動ですら破防法の適用ができない状況では難しいのか?)またわれわれ国民も小さな犯罪を許す事は大きな犯罪を生むことを忘れてはならないと思う。よく聞く言葉に「暴走族も一人だとかわいいものだよ」とか「子供の喫煙に対しては発見したら誰でも大人が注意をすべきだ」と言う。実際出来るのだろうか。補導員である私も大勢の補導員や少年係の署員の方々と一緒の行動だから声がかけられるのである。腑抜けと言われようが、催涙スプレーや警棒、暴漢に備えての確保技術等持ち合わせていない丸腰の自分に何を持っているかわからない若者に立ち向かうには数での威勢を張るしかない。
また、行政も暴力の無い社会づくりや明るい社会をつくる運動等街頭でティッシュを配るテレクラと同じような行動は意味がないと思う。特に明るい社会を作る運動は法務省が刑期を終えた者の人権擁護のための運動であるが、犯罪を犯したものがリスクを負うことは当然の報いである。だからこそ罪を犯してはならないのである。犯罪に寛容になり過ぎた日本の将来を憂い、過激な発言、不適切な表現もある事は承知しているが、法治国家である日本ではその法に従う義務を負うことは当然であり、真面目に働き、真面目に生活をするものがそれを侵す者を自らの人生を犠牲にしてまで守り保護する必要はない事だけ伝えたかったのである。
駐輪場の整備はどこの仕事?
3月26日、小田原市自転車等駐車対策協議会が開催された。その席上、行政側から小田原駅自由連絡通路工事に関わる既存自転車駐車場の閉鎖及び新自転車駐車場整備計画が示された。それによると小田原駅東口自転車駐車場(有料)はお城通り再開発事業の交換用地として平成13年3月31日をもって閉鎖。西口自転車駐車場は東西自由連絡通路完成時までにJR東海に業務用通路として徐々(平成13年8月までに一部閉鎖、平成15年3月に完全閉鎖)に閉鎖される。この閉鎖に伴い、旧職安通りにある栄町2丁目鉄建公団用地を整備し、平成13年度8月には600台を。平成15年4月には1000台を収容する駐輪場計画がある。平成13年度当初予算では、小田原駅周辺に限らず、自転車駐車場経費として5,288万4,000円が計上されている。そもそも駐輪場の整備は行政がやらねばならない施策なのであろうか。「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」によれば、
第5条 地方公共団体又は道路管理者は、通勤、通学、買物等のための自転車等の利用の増大に伴い,自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域においては、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努めるものとする。
2 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における前項の自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように,地方公共団体又は道路管理者との協力体制の整備に努めるとともに,地方公共団体又は道路管理者から同項の自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡,貸付けその他の措置を講ずることにより,当該自転車等駐車場。設置に積極的に協力しなければならない。ただし,鉄道事業者が自ら旅客の利便に供するため.自転車等駐車場を設置する場合は.この限りでない。
3 官公署,学校,図書館.公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店.スーパーマーケット、銀行.遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し,その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内文はその周辺に設置するように努めなければならない。
とある。現状の小田原市に存在する駅は18駅。JR根府川駅、大雄山線緑町駅、穴部駅、飯田岡駅、箱根登山線風祭駅、入生田駅以外は駐輪場が設置されているが、大雄山線井細田駅、五百羅漢駅、小田急線富水駅を除きほとんどが設置者、土地保有者として小田原市が関与している。前述した法律とともに併せて「小田原市自転車等の放置防止に関する条例」にも市の責務、鉄道事業者等の協力が明記されており、行政としてはその責務を果たしているとみられるが、鉄道各社は行政施策に積極的に協力しているかは疑問である。少なくとも用地についての現状をみると、協力体制がとられているとは思えない。また商店街などに溢れる自転車も、商店街利用者が置く自転車を行政施策だけに任せるのではなく、第5条第3項と同様に商店街としての対策を講じる必要があると思う。受益者負担の原則からして、公共的側面と、その施策実施により利益を生む企業との負担割合や利用者に対する応分負担も視野に入れた有料駐輪場(但し、駐車場と同じく利用者へのサービス券の配布等も考慮することも含め)とともに、放置自転車が溢れる地域には、国府津、鴨宮駅と同様に放置自転車禁止区域を拡大せざるを得ない。
このことは、利用者モラルにも帰することもあり、特に小田原駅周辺における放置自転車の実態及びその警告、移動、保管、処理にいたるまでの経過について、現在の方法が良いのか他の手段も考える必要があるのかも議論をしていく必要がある。(H13.3.30)
卒業式
今日は中学校の卒業式だった。卒業式といって連想するものは?と聞かれれば「蛍の光」「仰げば尊し」と答えるのは過去の人かもしれない。今やこの歌もしくはメロディを流す学校はいくつあろうか。
卒業式はそれぞれの学校で工夫を凝らして演出することに否定はしない。しかし、敢えて意図的にこの曲を使わないということなのか、真相はわからないが、久しく聞いていない。聞いていないから無性に歌いたくなってついカラオケで歌ってしまう。(誰だか忘れたがちょっとアレンジした仰げば尊しがある)
「身を立て、名を上げ」これが平等に反するというのか、明治17年の文部省唱歌でお上からの押しつけだからと言うのか、答えはわからない。でも卒業式には是非歌ってもらいたい歌である。私が出席した学校の卒業生による歌の歌詞をみると「自然」「大地」「空」など人間に対する感謝の台詞は無い。自らが大自然に羽ばたくような歌詞である。これはこれでいいが、やはりこの学校生活で世話になった恩師、校舎などへの感謝と別れの辛さ、そして友を気遣い共に励ますという誰もが胸打たれる歌は他に見当たるだろうか。自然との関わりもさることながら、人と人の出会い、そして自らの成長には、過去も未来も必ず人が関わるのである。人生の節目にこんなにふさわしい歌を祖父や父も歌っていた。「卒業」という共通点とともに。
ホームページで「仰げば尊し」で検索すると相当な数である。その殆どが何故歌わなくなったのかという疑問の声が多いように感じる。斉唱しない事が学級崩壊の一因として捉える方々もいるが、それだけ先生は師として仰がれる存在なのだという事を先生方はしっかり自覚してもらいたい。そして胸を張って卒業生が歌う仰げば尊しを受けてもらいたいものである。
制服自由化についても、それを罪悪視する風潮もある。わが母校は一部の者の煽動によって生徒会がこれに従い現在制服自由化が実施されているようである。しかしながら、高校受験期には制服を求める生徒が兄や姉の制服を借りたり、近所の卒業生から制服を借りたりしていると聞く。子どもの方が世間を知っているということだ。3月9日の日記には在校生(特に女子)の制服(過去の制服だったり高校生風の制服)着用率が非常に高かった。そろそろ自由化なんぞはやめて素晴らしい制服を作ってみたらどうか。他校生徒が憧れる制服を着て優越感に浸る。不謹慎かも知れないが、母校への愛着や自覚を促す上では少なからず寄与するかもしれない。(H13.3.9)
教育について
戦後50数年の間に完全に国家としての威厳や誇りを失ってしまった日本。弱腰な外交姿勢。横行する少年犯罪や毎日報道される殺人事件の数々。人権屋に征服されたマスコミと国民。21世紀の日本の将来に希望の光を見いだすのは、そもそも共同体の最小単位である家庭や家族を中心として、国民一人一人がしっかりとした目標を持ってこの危機から脱却する意外にないと思います。一刻でも早く正常な状態に戻すこと。それが政治家の務めです。日本の歴史、伝統、文化そして国家の存在すら否定してきた戦後の一部の大人たちが、発達したメディアを使って或いは学校教育の中で子供たちに自虐思想や悪平等主義を押しつけてきたことなど、我々をマインドコントロールしてきた時代は終わりです。正月の日の出暴走も荒れる17歳も援助交際も成人式でクラッカーを鳴らすのも、全て大人が築いてきた戦後社会の写し鏡です。大人が施した社会環境なのです。
教育は百年の計とも言われます。50年間を取り戻すには100年、150年と掛かるかもしれません。しかし様々な問題が一部でなく既に国民全体、身近な問題となった今こそ、乳幼児期からの母子の関係は如何にあるべきか。学校教育とは何であるか。子供が安全に安心して過ごす事ができる社会環境はどうあるべきか。もう議論の余地はありません。国が健全な子供たちを育てるための基本理念、指針を示し、大人はその理念に基づいた行動をする。営利主義、拝金主義の業者やマスコミへは毅然とした態度をもって対応できる政府でなければなし得ないことであると思います。
昨年小田原市議会は青少年健全育成基本法の制定を求める意見書を国に提出しました。今や全国の地方自治体からも同趣旨の決議や意見書が出されております。政界のゴタゴタ劇は御免です。国家の基本である教育問題について、これからも本腰を入れ、取り組んでいきたいと思っています。(H.13.1.20書)